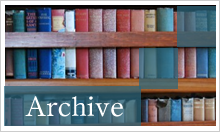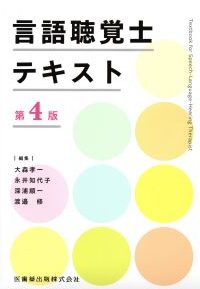教室概要
大阪医科薬科大学形成外科学教室は、1982年10月に新設された。
初代教授として、慶応大学医学部形成外科助教授より故 田嶋定夫 教授(1964京大卒 )が着任された。
形成外科外来は、初期より口蓋裂言語の専門家を招き、唇裂・口蓋裂の集学的治療をめざした言語治療外来や、専門のメディカルエステティシャンによる遊離植皮術後や、熱傷瘢痕に対するメディカルソワンエステティック外来(美容技術を応用した後療法)など、特色のある外来診療体制は固められた。
病棟は、成人を対象として外科系混合病棟として開設され、唇裂・口蓋裂を初めとする体表面の先天異常や、Cranio-Maxillo-Facial Surgeryなどに対応するため新たに小児外科系専門病棟が開設された。
1986年には、犬咬傷による剥奪外鼻の再接着にわが国で初めて(世界で2例目)成功し、以後マイクロサージャリーを用いた各種再建を積極的に行い、頭蓋顎顔面外科とともに臨床手技の新たな支柱を形成した。
教室では、初期から皮膚組織保存や創傷治癒促進に関する研究に取り組み、ケロイド肥厚性瘢痕の生化学的研究、皮弁の再灌流障害の研究を大きく発展させていった。
また頭蓋顎顔面の先天異常、骨折や変形治癒に対する三次元実体模型作成システムを1992年より導入し、シミュレーション手術、各種三次元計測を充実させていった。
ついで2000年よりQスイッチアレクサンドライトレーザー、IPL、ケミカルピーリングが導入された。
2001年1月田嶋定夫教授逝去後は、上田晃一助教授(当時)を中心に診療が行われ、多施設との共同研究を推進した。
2004年10月、第2代教授として上田晃一教授が就任した。
同年よりダイレーザーも導入し、レーザー治療の範囲が広がった。
その後北里大学人工皮膚開発センターと共同研究を始め、倫理委員会承認の後、同種培養真皮を用いた難治性潰瘍や熱傷創の治療を開始した。
さらに北里大学と自家培養真皮の臨床応用を共同開発し、広範囲小児熱傷瘢痕の治療や口蓋裂手術に応用し始めた。
また頭蓋顎顔面領域の先天異常に対して骨延長器を用いた治療を積極的に行い、またマイクロサージャリーの分野では犠牲の少ない穿通枝皮弁やリンパ管静脈吻合によるリンパ浮腫の治療を行っている。
2025年4月、第3代教授として塗隆志教授が就任した。